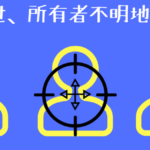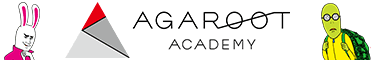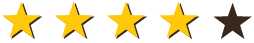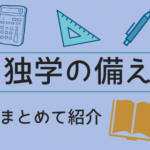こんにちは、ゆうぞうです。
私たちが普段建物調査をおこなう時、建物周りと敷地からの離れを測って、構造や屋根などを確認して・・・・・
と当たり前のように調査をおこなっていると思います。
しかし、そもそもの根底の話ですが、
私たちの扱う「建物」とはどのようなものを指すのでしょうか。
一般的な住宅は当然に「建物」として扱いますが、周壁のないカーポートや簡易的なイナバ物置はどうでしょうか?
土地家屋調査士は不動産登記法に準じて、調査・測量をおこない、登記をしますので、不動産登記法で規定しているとおり「建物」と認定していくわけですが、実務上で判断に迷う建物が多いように感じます。
また、建築基準法と不動産登記法でも建物(建築物)の考え方が異なりますので、建築確認申請の面積と登記簿床面積が異なるケースも多々あります。
建物登記をおこなう上で、思考の根底部分をしっかりと確認することは大変重要なことです。
ですので、今回は「建物」における基本的な「概念」と「建物認定」について再確認していきたいと思います。
Contents
建物の概念について色んな角度から確認しましょう
建築基準法における建築物
建築基準法第2条第1号では、
建築物とは土地に定着する工作物のうち, 屋根若しくは壁を有するもの,これに附属する門若しくは塀,観覧のための 工作物又は高架の工作物内に設ける事務所,店舗,興業場,倉庫その他これ らに類する施設(鉄道及び軌道の路線敷地内の運転保安に関する施設並びに 跨線橋,プラットホームの上家,貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。) をいい,建築設備を含むものとする。
と定義されています。
建築基準法は国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的としているので、
例えば,工作物のうち,門・塀については,「空き地に門・塀の みがある場合は,建築物とはならないが,建築物に附属する門・塀について は,建築物となる。」と解釈されており、不登法上の建物よりも広義的な概念となっています。
民法における建物
民法では第86条第1項で、
と規定されていますが、どのようなものを「建物」とするかまで明文規定していません。
不動産登記法における建物
不動産登記実務上では,不登規第111条で、
建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
と規定しており、不登準第77条で、
建物の認定に当たっては,次の例示から類推し,その利用状況等を勘案して判定するものとする。
一 建物として取り扱うもの
ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし,上屋を有する部分に限る。
イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし,屋根を有する部分に限る。
ウ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物
エ 地下停車場,地下駐車場又は地下街の建造物
オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし,半永久的な建造物と認められるものに限る。
二 建物として取り扱わないもの
ア ガスタンク,石油タンク又は給水タンク
イ 機械上に建設した建造物。ただし,地上に基脚を有し,又は支柱を施したものを除く。
ウ 浮船を利用したもの。ただし,固定しているものを除く。
エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)
オ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等
と規定しております。
具体例を挙げて「建物として取り扱うもの」あるいは「取り扱わないもの」を定めていますので、これを基準に建物とするかどうかの判断をします。
また不登法上の建物として認められるためには次に挙げる要件を満たす必要があるとしています。(建物認定参照)
不動産登記法における建物要件
外気分断性
外気分断性とは建物内部に外気を自由に出入りすることを防止していること、つまり屋根および周壁等が存在しているかどうかで判断します。
しかしこれらの判断は必ずしも物理的に構築されているか問うものでは無く、
「周壁の有無、程度」「材質の耐久性」「例外的な取扱い」「駐車場の取扱い」
を勘案し総合的に判断していく必要があります。
例を挙げると、
ゴルフの練習場は打球が飛ぶ方向は開放されていますが、「建物」として登記可能だったり、排気ガスを排出する為に周壁が開いている立体駐車場は「建物」として認定されます。
定着性
建物は土地の定着物ですので、物理的に土地に固着し、永続的に定着している必要があります。
判断要素として、
「固着性」「船を利用するケース」「土地以外への固着」「永続性」
があり、これらを基本として判断します。
例えば、前述した簡易的なイナバ物置ですが、
コンクリートブロックの上にただ定着させたものであれば、定着性不十分として「建物」としませんが、コンクリート基礎をしっかりと施工されたものであれば「建物」として認定されるわけです。
用途性
建物は一定の用途の為に造られるものなので、その用途に見合った生活空間が確保される必要があります。(人貨滞留性)
例えば、土地家屋調査士の中では有名な案件ですが、
鎌倉市にある「大船観音寺の観音像」と「高徳院の大仏」が挙げられます。
「大船観音寺の観音像」は内部に祭壇が設けられ、参拝者の着席が可能な施設や本堂としても利用されていることから、「建物」として認定されます。

逆に「高徳院の大仏」は内部に入ることは可能ですが、内部を利用する施設等が無い為、用途性を欠くことから「建物」としていません。

取引性
建物自体が「不動産」として取引されるに値するものであるかどうかも重要であるとの考えられており、土地家屋調査士の基本理念である不動産の取引を安全かつ円滑に図るための制度を考慮されています。
最後に
私たち土地家屋調査士にとって、建物登記は短期間で件数をこなす事ができますし、業務依頼があると大変ありがたいものです。(経営的な意味で)
また隣接地所有者との折衝事もありませんので、
建物登記は簡単というイメージを持つ方もいらっしゃいますが、建物の登記をおこなうには多くの知識と判断力が求められる為、意外と難しいものです。
知識と判断力は実務をこなすうちに備わってくるものだとは思いますが、私たちの仕事は1つのミスが致命傷になるケースが多く、いつも緊張感をもち慎重におこなうべき仕事です。
ですので、調査士法第2条にもありますが業務に関する法令及び実務に精通する為、生涯勉強が必要だなと感じる次第です。
また、建物登記のバイブルともいえる「建物認定」は一度目をとおすと、建物登記の思考が定着すると思います。
まだ見たことがない受験生の方、是非試験前に一読するようにしましょう。

「スキマ時間で択一問題」のカテゴリで
受験生皆様の電車通勤、お昼時間、就寝前の15分などの
スキマ時間の有効活用にちょうど良い択一問題を配信しています。
お手隙の時間にご活用下さい。
最後までお読みいただきありがとうございます。
それでは、また。

にほんブログ村

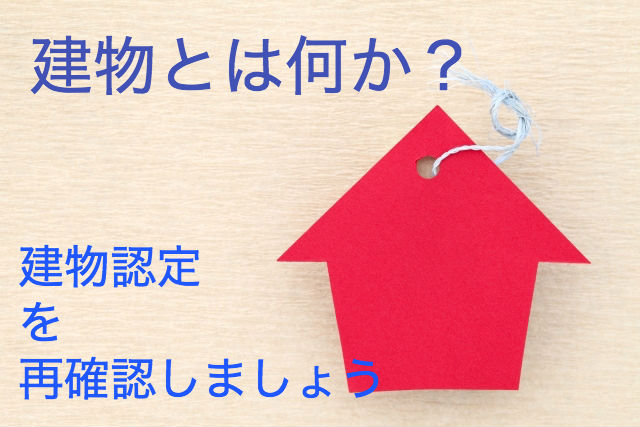


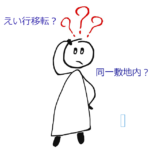
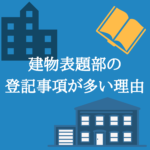
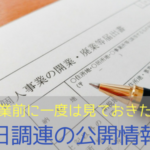
![[測量tips]先細プライヤ](https://hikkainokanata.chosashi-sato.com/wp-content/uploads/2019/05/測量tips先細プライヤ-2-150x150.png)