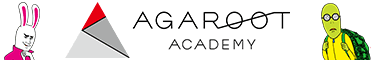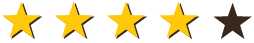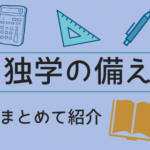本日は建物の登記事項についてです。
電車での通勤時間や移動中のスキマ時間で回答できるボリュームです。
頭の体操にいかがでしょうか。
問1
出窓はその高さ1.5m以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に参入する。
答 ○
出窓はその高さ1.5m以上のものでその下部が床面積と同一の高さにあるものに限り床面積に参入します。
問2
柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、各階の床面積に接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。
柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、各階の床面に接着する壁その他区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によって求めます。
問3
建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分は上階の床面積に参入しない。
建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分は上階の床面積に参入しません。
また、手すり階段や吹抜けが接する階段室は床面積に参入しないケースがあります。
問4
開閉式の屋根を有する建物における開閉式屋根の開閉可能な部分の下に当たる部分は、床面積に参入しない。
開閉式屋根については、開閉可能な部分の下に当たる観客席及びフィールド部分も床面積に参入することができます。
問5
独立性のある2棟の高層建物を往来するために2階部分に工作した建物の通路は、床面積に参入しなければならない。
独立性のある2棟の建物が連絡通路により接続している建物は、格別に一棟の建物として取り扱います。
つまり、通路部分は通路に利用されているに過ぎず、用途性がないとされます。つまり通路部分は床面積に参入されず、1棟の建物ずつ建物登記をおこなうことになります。
今回は「建物の床面積の定め方」についてでした。
床面積を考える時に覚えておく事項は不動産登記規則第115条と不動産登記事務取扱手続準則第82条です。
これについては六法を開いて確認するほか、「建物認定」で写真や図解を確認するとより理解が深まるはずです。

「スキマ時間で択一問題」のカテゴリで
受験生皆様の電車通勤、お昼時間、就寝前の15分などの
スキマ時間の有効活用にちょうど良い択一問題を配信しています。
お手隙の時間にご活用下さい。
最後までお読みいただきありがとうございます。
それでは、また。

にほんブログ村